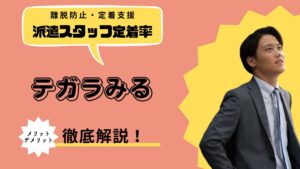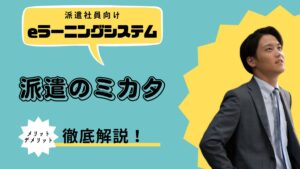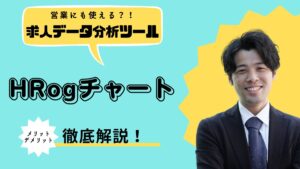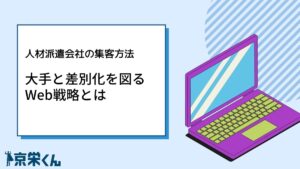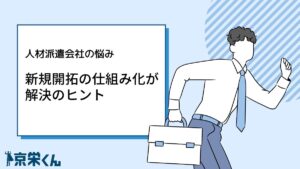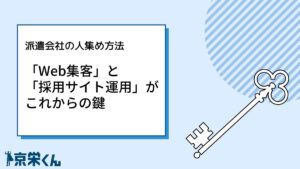求人活動を行う際に、「自社の採用単価は他社と比べてどうなのか?」「抑えられる費用はないだろうか?」など気になっている方も多いのではないでしょうか?
有能な人材をより低単価で獲得したいと、どの企業も考えますよね。
ただ、実際にどのように改善すれば今よりも採用単価を下げることができるのか、知らない担当者の方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、採用単価の平均相場や、採用単価を下げる方法についてご紹介していきます。
採用コストの削減方法はこちらも参考にしてみてください。

そもそも採用単価とは?計算方法は?
採用コストとは、人を採用するための活動にかかる費用のことです。
採用を行う際には、「求人サイトに広告を掲載する」「会社説明会を行う」など、どうしても費用がかかってしまいます。
この採用コストから人一人当たりにかかる費用を計算したものが、採用単価です。
企業が人材獲得に割けられる費用には限りがあるので、採用単価をできるだけ下げて人材を獲得したいですよね。
採用コストを削減するためには、採用コストだけに注目するよりも、採用単価を重要な指標とすることで見直しがしやすくなります。
どのようにして採用単価を下げるかが、採用担当者の大きな課題でしょう。

採用単価の平均相場は?
ここでは以下の項目に分けて採用単価の平均相場を紹介していきます。
- 年度別
- 企業規模別
- 業界別
「年度別」の平均採用単価
リクルートが行った調査によると、平均採用単価は以下の通りです。
2019年度に中途採用にかかった平均採用コストは103.3万円、新卒採用にかかった平均採用コストは93.6万円です。
2018年度と比べると、平均採用単価は増加傾向にあることがわかります。
また、株式会社マイナビの「2023年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」によると、採用全体にかかる費用としては1社あたり平均約298.7万円というデータもでています。
■採用費総額平均
全体:約298.7万円/上場企業:約771.9万円/非上場企業:約267.4万円■入社予定者1人あたりの採用費平均(1社ごとに採用費を入社予定の人数で割った数値の平均値)
2023年卒マイナビ企業新卒内定状況調査
全体:約45.0万円/上場企業:約38.1万円/非上場企業:約45.5万円
その上、これだけのコストをかけたとしても、必要な人数を獲得できなかったり、せっかく採用した人材がすぐにやめてしまったりなどの事態もありうるので、多くの企業がこの採用単価の高さに頭を悩ませているのです。
「企業規模別」の平均採用単価
リクルートが行った2019年の調査によると、2018年度における企業規模別の平均採用単価は以下の通りです。
| 企業規模 | 新卒採用 | 中途採用 |
|---|---|---|
| 5000人以上 | 59.9万円 | 78.5万円 |
| 1000人~4999人 | 72.9万円 | 108.5万円 |
| 300人~999人 | 80.2万円 | 83.0万円 |
| 300人未満 | 65.2万円 | 63.6万円 |
| 全体 | 72.6万円 | 84.8万円 |
企業規模別でかかっている採用単価に特徴があることがわかります。
5000人以上の大企業は「ネームバリューがある」「1度に多くの新卒を採用している」などの理由から新卒の採用単価が下がっているのでしょう。
1000人~4999人の企業では中途採用に非常に力を入れていることがわかります。
「業界別」の平均採用単価
リクルートが行った2019年の調査によると、2018年度における業界別の平均採用単価は以下の通りです。
| 業界 | 新卒採用 | 中途採用 |
|---|---|---|
| 建設業 | 69.4万円 | 97.8万円 |
| 製造業 | 69.7万円 | 102.3万円 |
| 流通業 | 67.7万円 | 55.5万円 |
| 金融業 | 84.8万円 | 58.2万円 |
| サービス・情報業 | 78.1万円 | 86.8万円 |
| 全体 | 72.6万円 | 84.8万円 |
業界によっても単価は大きく異なり、建設業や製造業は中途採用の単価が高いのに対して、流通業や金融業では新卒採用の単価が高くなっています。
建築業、製造業の中途採用は専門知識や資格が必要な人材を求めることも多く、「一度に採用できる人数が少ない」「専門性を見極めるために選考が厳しい」などから単価が高くなっていると考えられます。
職種ごとの採用単価の平均と変動
各職種における採用単価の平均と変動は、企業が人材を確保するための重要な指標となります。
IT関連職種では、急速な技術の進化や需要の変動が採用単価に影響を与えています。
特に高度なスキルが求められる職種では、平均採用単価が相対的に高くなる傾向が見られます。
医療・看護職種では、医療ニーズや看護師不足の影響を受け、採用単価に変動が生じています。製造業では、技術系と労働系の職種で採用単価に差異があり、業界の需要変動が変動要因となっています。
販売・サービス職種では、消費動向の変化や季節性が影響を与え、これが職種別の平均採用単価の変動に繋がっています。金融・銀行職種では、金融市場の動向や需要に応じて採用単価が変動しており、市場の不確実性が採用に影響を与えています。
クリエイティブ職種では、デザインやクリエイティブスキルの需要変動が採用単価に反映され、人材の専門性が採用コストに影響しています。教育・トレーニング職種では、教育ニーズの変動が平均採用単価に影響し、業界の特異性が採用コストの変動に寄与しています。
これらの変動要因を理解し、各職種ごとに最適な採用戦略を検討することが、企業が効果的に採用単価を最適化する鍵となります。
業界や市場の特性に敏感に対応し、求められる人材像を的確に把握することで、効率的かつ経済的な採用活動を展開することが可能です。
\初期費用0円で掲載可能!/
\応募が来るまで0円の特化型サイト!/
新卒と中途の採用単価について
新卒採用では、一般的に教育プログラムやトレーニングへの投資が必要であり、これが平均採用単価を高める要因となります。
一方、中途採用では経験者のスキルや即戦力性が重視されるため、職種ごとに異なるスキルセットが求められ、これが中途の平均採用単価の変動に影響します。
例えば、IT関連職種では新卒採用よりも中途採用の方が経験を考慮して高額になることが一般的です。一方で、製造業の一部職種では新卒の方がトレーニング期間を経て即戦力になりやすいため、新卒の平均採用単価が高い傾向が見られます。
職種ごとのニーズや労働市場の特性を踏まえ、新卒と中途の採用単価を最適化するためには、それぞれの採用プロセスと期待される成果に焦点を当てた柔軟かつ戦略的な採用計画が求められます。
【2023年】採用単価の今後の推移
採用単価はさらに増えていくことが予想されています。
リクルートが行った調査によると、2022年に採用実施した企業の中で、2023年の採用活動に費やす費用の見通しが「増える」と答えた企業は、「減る」と答えた企業の2倍以上ありました。
企業採用担当者からみる新卒採用のコスト推移の見通し
<2023年の採用活動に費やす費用の見通し>
| 企業規模 | 増える | 同じ | 減る |
|---|---|---|---|
| 5000人以上 | 22.3% | 64.9% | 12.8% |
| 1000人~4999人 | 25.9% | 63.9% | 10.2% |
| 300人~999人 | 23.4% | 68.5% | 8.2% |
| 300人未満 | 20.3% | 68.6% | 11.0% |
| 全体 | 22.9% | 67.1% | 10.0% |
<2024年の採用活動に費やす費用の見通し>
| 企業規模 | 増える | 同じ | 減る |
|---|---|---|---|
| 5000人以上 | 34.0% | 54.6% | 11.3% |
| 1000人~4999人 | 36.5% | 59.2% | 4.3% |
| 300人~999人 | 30.1% | 63.2% | 6.7% |
| 300人未満 | 27.6% | 62.1% | 6.6% |
| 全体 | 31.3% | 62.1% | 6.6% |
リクルートが行った調査によると、2024年卒採用の見通しとしても採用活動に費やす総費用は全体的に増えると回答されており、「減る」とみている企業は6.6%にとどまっています。(出典:株式会社リクルート「就職白書2023」データ集)
どの規模の企業でも「採用コストが増える」と答えた割合が高く、規模に関係なく採用コストは増加傾向にあります。
少子高齢化などの影響による「人手不足」「市場の激化」で、コスト増加を感じる企業が多いのが現状です。
中途採用のコスト推移
こちらは、株式会社マイナビの中途採用状況調査のデータです。
<2022年の中途採用活動にかけた費用>
| 企業規模 | 採用予算 | 採用実績 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 458万円 | 360万円以上 |
| 51~300人 | 272万円 | 277万円 |
| 50人以下 | 132万円 | 104万円 |
<2023年の中途採用活動にかけた費用>
| 企業規模 | 採用予算 | 採用実績 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 667.8万円 | 598.3万円 |
| 51~300人 | 354.8万円 | 310.7万円 |
| 50人以下 | 187.7万円 | 151.7万円 |
実際に中途採用活動にかかった費用も、事前の予算も前年に比べると高くなっていることが分かります。
人材確保に対して難しかったと感じている採用担当者も多かったようです。
また今後の中途採用見通しとしては、経験者採用の積極的採用よりも、未経験者採用を積極的に行う意向が高まっており、以前として経験者採用に積極的ではあるが、未経験者採用にも力を入れ始める傾向が強まる見通しが出ています。
平均離職率の推移
厚生労働省発表の「令和4年雇用動向調査結果」によると、令和4年1年間で一般労働者については離職率が入職率上回った一方、パートタイム労働者については逆に入職率が離職率より高く女性とパートタイム労働者は入職超過、男性と一般労働者は離職超過となっていました。
令和4年1年間の入職者数は 7,798.0 千人、離職者数は 7,656.7 千人で、入職者が離職者を 141.3千人上回っている。
一般労働者の入職率が11.8%、離職率が11.9%、パートタイム労働者の入職率が 24.2%、離職率が 23.1%で、女性とパートタイム労働者は入職超過、男性と一般労働者は離職超過となっている。
厚生労働省発表「令和4年雇用動向調査結果」
なぜ高騰?採用単価が上がってしまう要因
採用単価を下げるためには、現状の採用単価を把握する必要があります。
まずは、採用単価が高くなっている要因を見直すことから始めましょう。
採用単価が上がる要因①能力の高い人材を獲得しようとしている
即戦力として能力の高い人材を獲得したい場合、どうしても採用単価が上がってしまいます。
現在はどの企業も人材が足りていない上に、少子高齢化に伴い人材が少なくなっています。
そのため、その中からより能力値の高い人材だけを採用しようと考えた場合、どうしても採用単価は上がってしまうのです。
採用単価が上がる要因②たくさんの媒体に求人を出している
より多くの人材を獲得したい場合、求職者がどの求人サイトを見ているのか分からず、複数のサイトに求人掲載している方も多いのではないでしょうか。
その場合、すべてのサイトの掲載費用を負担する必要がありますので、採用単価は必然的に上がってしまいます。
採用単価が上がる要因③同じ採用ツールを導入したままになっている
採用活動を効率化するために採用ツールを導入した場合、その効果を測定せずに次年度も同じ方法が取られている企業は多いのではないでしょうか?
特に昔ながらの慣習を大切にしている場合、それまでのやり方を維持する場合も多いようです。
また、人材の入れ替わりが激しい企業でも前任者からの引継ぎが行われておらず、気づかないうちに費用を払ったままになっているというケースも多くあります。
採用単価を下げるための4つの方法
では、実際に採用単価を下げるためには、どのような方法を行えばよいのでしょうか?
具体的な4つのコスト削減方法は以下の通りです。
- 現在かかっているコストをチェックする
- 母集団形成をしっかりと行う
- 掲載する求人サイトを厳選する
- 無料の求人方法や、成果報酬型の求人方法を利用する
採用単価を下げる方法①現在かかっているコストをチェックする
現在かかっているコストを見直すことで、コストの無駄を浮き彫りにでき、採用単価を下げることができるでしょう。
採用活動における無駄を省くなら採用業務の効率化を進めるのがおすすめです。
採用単価を下げる方法②母集団形成をしっかりと行う
母集団形成を効果的に行うことで「応募者の質の向上」「入社後のミスマッチ防止」が期待できるため、コスト削減につながります。
「良い応募者がなかなかいない」「せっかく採用しても離職率が高い」という場合は母集団形成に力を入れてみてはいかがでしょうか。
採用単価を下げる方法③掲載する求人サイトを厳選する
掲載する求人広告を費用対効果の高いものに絞るだけで、採用単価の改善につながります。
自社に合った求人方法に絞ることで、広告費用の削減だけでなく、採用担当者の工数削減や、応募の質の向上にもつながるため、効果の高い手法です。
採用単価を下げる方法④無料の求人方法や、成果報酬型の求人方法を利用する
無料や、成果報酬型の求人方法を利用することで、採用単価を下げることもできます。
これらの求人方法はリスクがないため、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
\初期費用0円で掲載可能!/
\応募が来るまで0円の特化型サイト!/